皆さんこんにちは。Rakuです。
「初めてのレポートどう書けばいいかわからない」
「バイトで忙しくてあまり時間をかけれない」
そのような悩みを持つ方も少なくないのではないでしょうか。
実はレポートや論文を執筆するのってAIを使えば大幅に効率化できるんです。
でもそれって不正なんじゃないの?
確かにすべての作業をAIに行わせるのは不正かもしれませんが、AIを補助として使うのであれば不正ではありません。
むしろこれからの社会で生きていくためにはAIを自分の作業にどう上手に組み入れるかが大事になります。
この記事を読めば、レポート・論文の書き方がわからない方でも、どうやって作業を進めればいいかがわかり、大学でも他生徒より圧倒的に効率よく作業を終えられること間違いありません。
論文を書くまでの手順
以下がレポートや論文を書く際の主な手順になります。
①研究分野を特定する
②先行研究・本などを読む
③研究課題を決める
④実験or調査を進める
⑤分析
⑥執筆
※⑤分析と⑥執筆は同時に行わう人もいますが今回はわかりやすいように別の段落にしました。
では、これから各段階でどのようなAIを使い作業を効率的に進めるかを説明します。
研究分野を特定する
研究分野を特定する、この分野だけはAIを使えません。
自分の興味ある学術分野を探して、教授と一緒に研究分野を特定しましょう。
先行研究・本などを読む
先行研究探しって結構大変ですよね。
ですが、Consensusを使えば先行研究を特定するのは容易です。
Consensus AIは、論文検索に特化したAIなので、Chatボックスに自身の興味のある学術分野の質問をすると、その分野に関係のある論文をたくさん表示してくれます。
以下は、Consensus AIについて詳しくまとめた記事なので、ぜひ合わせてお読みください。
また、読む論文が決まったら、読む前にそのpdfデータをGoogle notebookLMに入れ要約をさせましょう。
しっかりと読む前に論文の要約を見ておくと、実際読んだとき内容が簡単に理解できるようになります。
以下の記事はGoogle notebookLMについての詳しい記事なので、ぜひ合わせてお読みください。
研究課題(Research Question)を決める
ここで役立つのは皆さんご存じチャッピーことChatGPTです。
ChatGPTはほかのAIと比べてもその会話性能は高いです。
そのため、ChatGPTを通して研究課題の構想を練り上げるのは非常に有効な使い方だと思います。
しかし、ChatGPTに研究課題を考えてもらうのは避けましょう。
AIは、過去に学習したデータから回答を作成するため、ChatGPTの立てた研究課題は誰かの研究の剽窃であるかもしれません。
そのため、ChatGPTを使うときは「○○という研究課題についてどう思う?改善点はある?」などという質問をするように心がけましょう。
ChatGPTについて詳しく知りたいかたは、以下の記事を合わせて読んでみてください!
実験or調査を進める
実験
実験方法や調査方法を考えるときは、Perplexity AIを使いましょう。
Perplexityは検索機能に秀でたAIで、回答といっしょに情報源まで提示してくれるのが特徴です。
そのため、実験方法や調査方法をほかの大学や研究所のものを参考にできます。
しかし、実際に実験を進める際には特にこれといって使えるAIはありません。
なぜなら実験を行うのはあなた自身だから。
そのため、もしAIを使いたいなら、ChatGPTなどに「○○を証明するのに、この実験方法は適している?」などといった質問をするようにしてください。
Perplexityについて詳しく知りたい方は以下の記事を合わせて読んでみてください!
分析
分析には先ほども登場したGoogle notebookLMが最適です。
主な使い方としては以下が挙げられます。
・先行研究と自信の論文の草稿をアップロードし、結果の比較対比を行わせる
・グラフデータをアップロードし、検定を行わせたりする。
・先行研究をもとに自身のデータに生じた結果を分析させる
もちろん自分で分析することも非常に重要ですが、AIは自分にはなかった視点を提供してくれます。
多角的な分析を入れることで、あなたのレポートは高品質になります。
執筆
執筆は基本自分でまず草稿を書きます。この際、細かい文法や漢字ミスなどは気にせず、とりあえず一通り書いてみましょう。
そしてその草稿のデータをClaudeに「論文用に添削して」という命令とともにアップロードします。
ClaudeはほかのAIと違い、添削した文章をほかの文書として書き出してくれるので、それをそのままコピペしたら、きれいな文章の論文が出来上がります。
以下の記事では、Claudeについて紹介をしているので、合わせてお読みください。
まとめ
この記事では、論文のAIを使った効率的な書き方という内容を紹介しました。
先ほども言いましたが、論文そのものをすべてAIに書かせるのは絶対に避けましょう。
AIはあくまで自分の作業の補助、その意識を忘れずにいましょう。
また、以下の記事では論文を書くときに使えるOpenAI発の論文執筆プラットフォームPrismの紹介もしているので、是非合わせて読んでみてください!

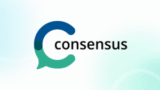
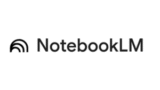






コメント